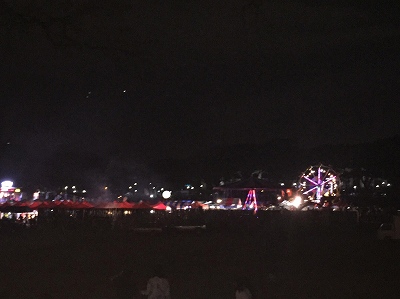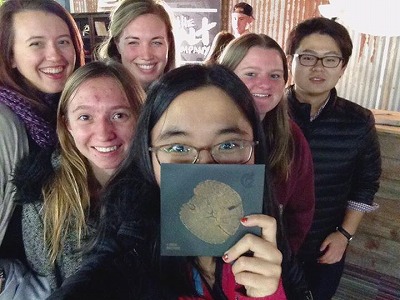今までの留学生活をふと振り返えると、毎日授業や課題をこなし、気づいたらもう7カ月。日本では学校と部活、アルバイトの両立で、ここでの生活よりもあわただしい毎日を送っていたが、ここでの生活はゆったりしていて良い。最近は自分が残りのフィリピン留学でやり残していることはないかと、考えて生活するようになってきた。
授業はオリエンテーションが終了し、本格的な授業になってきた。今学期から履修したコミュニケーションのクラスとスピーチのクラスは、とても人気がある授業だと多くの学生から聞いていた。そう聞いても、がっかりするのが嫌だったので、あまり期待はしていなかったが、今現在この二つの授業がある水曜と金曜は学校が楽しみで仕方がない。この二つの授業では、名前の通りコミュニケーションを取りスピーチをするのだが、その内容が何ともフィリピンらしいというか、おしゃべりが大好きな国だなと感じられるものである。
例えばスピーチのクラスでは、1人に1枚ずつ話す内容のお題が書かれた小さな紙が渡され、そのお題に対し何でもいいので1分間、クラスメート全員の前で話し続けたり(お題は発表の直前まで見てはいけない)、自分の好きな歌の歌詞を感情を入れて読んだりする(自分はアナ雪の"扉開けて"を披露した)。コミュニケーションのクラスもスピーチのクラス同様、クラスメートの前ですべらない話をしたり、グループを作り先生が出したお題(例えば最新の家電製品)について30秒間で説明をしたりするという、なんともユーモアあふれる内容である。
これらのクラスの狙いは、多くの人の前で話すことに慣れること、そして聞き手をいかに自分の話に引きつけるかを学ぶことであり、どちらも生きた英語、聞き手の生きたリアクションを生で感じられる素敵なクラスだと思う。個人的には教科書で学ぶ英語なんかより、100倍は楽しくてためになる。
留学中、名古屋学院大学とフィリピン大学で決定的な差を感じたことがある。それは、プレゼンテーション能力とスピーチ能力の差である。はっきり言って雲泥の差がある。フィリピン大学の学生の中には、プレゼンテーションのためだけにスーツに革靴などと、服装にまで気を遣う人もいる。この二つのクラスは、今後留学をする学生に1番お勧めしたい。今後もこの二つのクラスを通して、フィリピンのトップ大学におけるコミュニケーション能力とスピーチ能力を身に着けていきたい。
授業外では、フィリピン大学で開催されたUPFAIR(ユーピーフェア)というバンドイベントに参加をした。規模とクオリティーは、名古屋学院大学の学校祭の約50倍程だった。このフェアは1週間、毎日夕方から朝4時まで続き、ライブの舞台の他に、日本のお祭りのように屋台が学校のグラウンドに立ち並んだ。このフェアには、フィリピンで一番人気のあるバンドグループや、他にも数多くのバンドグループが参加していたようで、学外からも多くの来場者が来ており、大学規模でなくマニラ規模で開かれていると感じた。 一番驚いたのが、グラウンド内に1週間限定で簡易遊園地が設置されたことだ。観覧車のようなものやバイキングなど、多くのアトラクションが設置された。どれも1回120円ほどで乗車できた。
いよいよ留学終盤。今後3か月も、充実した生活を過ごしていきたい。