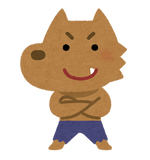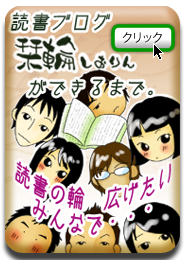図書館スタッフの最近のブログ記事
ごきげんよう、スタッフのかえるまんじゅうです。
みなさんには何か趣味はありますか?
語学、スポーツ、楽器、ダンスなどなど、サークルや個人で楽しむために日々努力している方もいらっしゃるでしょう。
今回ご紹介するのは、そういった何かしらに打ち込んでいる方におすすめの一冊です。
なぜ反復練習によって技術が身に付き上達するのか、初級者・中級者と上級者の違いはどういう所にあるのか、上達した人はどこが違うのか、などの論理面だけでなく、効率よく上達するための方法論についても書いてあります。
中級者から上級者にレベルアップするためにどうすればいいのか、どんなスキルにも応用できる具体的な練習方法も紹介されています。
どうせするなら効果的な努力をしたいですよね。
(なごやの図書館スタッフ かえるまんじゅう)
お待たせいたしました。
ただ今、瀬戸図書館では「教育実習」に備えた図書を展示しています。
展示コーナーをチェックしてくださいませ。
例年人気のおすすめ本から
今年新たに追加した本など30冊を展示しています。
『教育実習のよりよい授業づくり : 単元指導計画&学習指導案で学ぶ 新版』
『絵本で広がる小学校の授業づくり : 豊かな心と思考力を育む』などなど。
緊張する教育実習かと思いますが
体調に気を付けてくださいね。
皆さんの頑張りを応援しています。
(瀬戸図書館スタッフ 小豆)
人口1000万に満たない小さな国イスラエル。なぜこれほど世界のトップニュースになるのだろうか。
パレスチナとの武力衝突、イスラエルからの直接攻撃など、ニュースでやネットで現地の悲惨な状況を目にする機会が多い。国同士が争う理由は分からなくても、家を失い、家族を失い傷ついた人を見るたび心が痛む。
イスラエル人とパレスチナ人はどちらが正しいのか、どちらも間違っているのか。「どちらも、自分ではどうにもならない力の、お互いの、そして、自分自身の犠牲者なのである。」それをあぶりだす試みを著者は行っている。
この世界で最も複雑で、やっかいで、古代から続く紛争に注意を払うべき理由、紛争の解決を求める人びとを支援することが、中東のみならず世界にとっても重要である理由を語る物語である。国際社会の一員として"この国"を正しく理解するための入門書。
ぜひ、お読みください。
『イスラエル 人類史上最もやっかいな問題』/ダニエル・ソカッチ著
瀬戸の図書館員 とらねこ探偵ミロ
劇団四季劇場で上演されていたミュージカル『バケモノの子』を鑑賞しました。
今から10年程前に公開された細田守監督の同タイトルアニメーション映画が原作です。
どんなお話かザックリいうと・・・この世の中には、我々人間の世界とは別にバケモノの世界が存在していて、偶然バケモノの世界に迷い込んだ孤独な少年が、バケモノ達に愛され見守られながら成長していく・・・という物語です。
面白いのは勿論ですが『自分とは何者なのか』『自分は何を信じて生きていけば良いのか』など、成長していく上で誰もが感じる「自分と向き合うこと」の意味に光を当て背中を押してくれる感動の物語です。
生の舞台は迫力があるし最新の舞台美術でアニメ版『バケモノの子』のイメージを崩すことなく、綺麗で見事な演出をされていてとても感動しました。
実はこの原作のアニメ版DVD、なんと瀬戸図書館にもあるのです。
「誰だってみんな等しく闇を持っている。でもその闇に吞み込まれてはいけない。」
「忘れないで。私達いつだって、たった一人で戦っているわけじゃないんだよ。」
「胸の中で剣を握るんだよ。」
(私の心に刺さったセリフです(^_^;))
楽しい中にもとても奥の深いこの物語、ぜひ瀬戸図書館でDVDを視聴して感動で胸いっぱいになっていただけたらと思います。
(瀬戸図書館スタッフ:かるみあ)
皆さんはどんなことわざを知っていますか?
どんなことわざが好きですか?
有名なところだと「笑う門には福来る」あたりは
縁起の良いことわざですね
「果報は寝て待て」とか「好きこそものの上手なれ」とか
私は好きだったりします
こうしたことわざは世界にも似たような言いまわしがあり
それを日本のことわざを中心に一冊にまとめた
カラフルで分かりやすい本が本学図書館にありました
日本でなじみのあることわざが
世界では、外国語では
同じ意味でもこんな言いまわしになるのかと
その文化背景の差が見えて
ちょっと面白い一冊です
ちなみにこちらの本
「著者/北村孝一、協力/ことわざ学会」とあり
ことわざ学会なるものがあることを知りました
いろんな学会があるものですね
興味のある方はネットなどで調べてみてはいかがでしょうか
(図書館スタッフ:るん)
少し前「ゴールデンカムイ」という漫画の実写映画がヒットしました
元々作品のファンで、映画もとても楽しく拝見した一人です
この作品を通じてアイヌの文化に興味を持った方も多くいるでしょう
そんな方にこちらの本を紹介したいと思います
アイヌの女性マウコはヌプルクル(霊力を持つ人)です
マウコは出会った人々の協力を得ながら
オオカミの声をたどって
自身と自身を取り巻く状況に向き合っていきます
彼女の進む道には実際に存在している
アイヌについての博物館や資料室、
関係人物がたくさん登場します
そして、アイヌであること
それが今の日本でどういう状況なのか
どんな言葉を投げかけられ
どんな思いで過ごしているのか
その歴史的な複雑さも含めて
小説という形の中で自然と触れられるよう描かれています
ぜひ、作者の前書きと後書きも
合わせて読んでもらいたい一冊です
(図書館スタッフ:るん)
🌟今回紹介するのは
ちょっと長いタイトル
『ろうの両親から生まれたぼくが聴こえる世界と聴こえない世界を行き来して考えた30のこと』
著者 五十嵐大・発行 幻冬舎
私が手話を覚えたいな〜と思い始めたのは何十年も前のこと、仕事で手話を知っていたらと思う出来事があったこと、
それと同時期に教会で手話賛美を初めて見た時に美しいと感じたことなど。。。
でも学ぶ時間もなくて(言い訳ですが)
そのうち手話賛美の本で、何曲かマスターして、その表現のいくつかを組み合わせてカタコトで、ほんの少し本当にほんの少し話せるようになりました。そんな時、コーダの方と知り合うチャンスがあり、手話との関わりは広がっていきました。
コーダとは両親が聴覚障害者の方のことです。
この本は、そんなコーダの方が子供の頃からの体験を記してくださった本です。
手話を学ぶ上でもこの背景はとても大切なことだと思います。何より本人は自分で好んで聴覚障害になったわけでもなく、その子も選んでコーダとして生まれたわけでもない。この本を通して、聴こえる世界と聴こえない世界、両者の世界が広がることを祈ります。
私の手話は相変わらずカタコトですが、手話を学ぶ上で手話技術より、もっと大切なことがあると考えています。
「守る」のではなく「ともに生きていく」というタイトルで30のことは終わります。
可哀想、差別、怒り、恥、守らなければ、守れなかった、涙のありがとう、
そして行き着いた「ともに生きていく」という著者の言葉に、希望を感じました。
東日本大震災を体験したこのご家族の大変さは、短く簡単に書かれていますが、聴こえないご両親の避難の様子を読んで、周りの方々との繋がりの大切さを痛感いたしました。守られてよかった。
『ろうの両親から生まれたぼくが聴こえる世界と聴こえない世界を行き来して考えた30のこと』は瀬戸図書館にあります。
‼️関連図書‼️ドラマ化もされた『デフ・ヴォイス』もおすすめします。瀬戸図書館にあります。
(図書館スタッフ:小豆)
こんにちは、本日はおすすめ映画DVDの紹介です♪
『キングダム』
超人気コミックの実写映画シリーズです。
古代中国の春秋戦国時代末期における、7つの戦国国の
争乱背景とした作品。中国史上初めて天下統一を果たした
始皇帝と、それを支えた武将李信にまつわるストーリー。
(原作は2013年、第17回手塚治虫文化賞のマンガ大賞を受賞)
壮大な乱世のお話で、ハマっている方もいらっしゃるかと思います。
実写化もよく出来ていて、大変な人気作ですよね。
瀬戸の図書館にもシリーズで揃っています。
是非見に来てください♪
(★瀬戸の図書館スタッフ ティズ★)
内村鑑三の生き方、考え方にとても興味があって、最近は、関連の図書を難しいですが、あれこれ頑張って読んでいます。そんな中で、読みやすくアレンジされた本を見つけました。
内村鑑三の『後世への最大遺物』をわかりやすく、今の言葉に編集した
を紹介いたします。
まず、最初のページに紹介されてた漢詩のメモをシェアいたします。
天地無始終
人生有生死
意味:天地は永遠で、始めも終わりもない。人間には生死があり、人生には限りある。頼山陽(江戸後期の漢詩人)
残すといえば、お金?事業?、。。。そんな財産が欲しいと欲を持つのはいけないことか?
私には残せるものなど何もありませんが、
誰もが残せる唯一のものがある
と、内村鑑三は言っています。
今の私たちに足りないものはお金ではない
さて、それは?
この本を今、読む人への解説が後半に記されています。
この作品は内村のキリスト信仰を伝道するために書かれている本ではない。彼は宗教としてではなく、自己啓発として話した、とこの解説者は説明しています。
確かに聖書の話や福音についての内村鑑三の礼拝メッセージ的なものはなかったように思います。
しかし、彼の生き様を知る助けにはなると思います。
今日からの生き方が変わる、そんな一冊です。
文字も大きく、読みやすく編集されています。
ぜひ一度、読んで見てくださいませ。
内村鑑三に興味をもたれましたら、図書館の検索ページから探してみてくださいね。図書館には、内村鑑三に関する本がたくさんあります。『内村鑑三』で検索してください。
『図書館のページ』
‼️おまけ‼️
もう一冊おすすめいたします。
『内村鑑三とその周辺』は瀬戸図書館書庫にあります。図書館カウンターにお尋ねください。
※下の写真は内村鑑三の墓碑銘である言葉と私のお気に入りの写真です。私のアルバムより。
(図書館スタッフ:小豆)