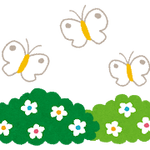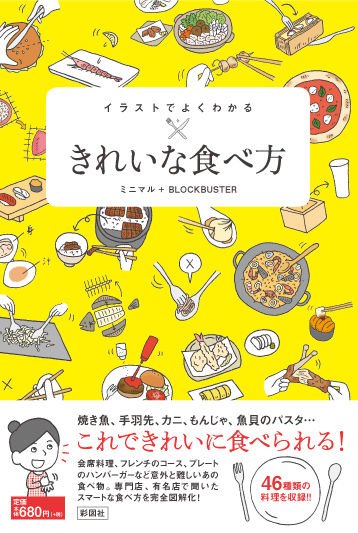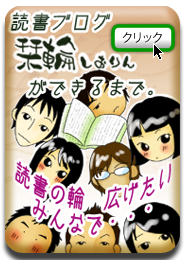オススメ本の最近のブログ記事
こんにちは♪ あかトマトです。
先日3年越しで待望の「安曇野ちひろ美術館」へ行ってきました❣
息子が長野県に引越してからこの3年、年に3回は長野に行っているのに、結局いつも息子の部屋の掃除や買い物に追われ...やっと今回念願が叶いました☆
あいにくの大雨で本来なら安曇野の美しい景色も見られるはずだったのですが、それは叶わず...でも駐車場から美術館の入口まで傘の貸出をしていたり、入る前から来館者に優しい美術館でした。
私は幼い頃に読んだ絵本『ひさの星』が好きで、いわさきちひろの絵のファンになったのですが、絵心は全くなく...
ただ素敵だなぁという感覚なのですが、油絵を習っている娘は食い入るように長時間かけて観ていました。
それでもド素人の私の心にも響く、あの透き通るようないわさきちひろの絵の美しさに囲まれて、本当に来てよかったなぁと思える素敵な時間でした。
館内には信州産のりんごジュースやアイスティー、地元のお菓子やパンをいただける「絵本カフェ」もあり、お土産も充実していて、特にいわさきちひろのファンでなくても年齢問わず1日楽しめる場所です♪
長野へ行った際には、ぜひ一度訪れてみてくださいネ☆
(なごやの図書館スタッフ:あかトマト)
ごきげんよう、スタッフのかえるまんじゅうです。
みなさんには何か趣味はありますか?
語学、スポーツ、楽器、ダンスなどなど、サークルや個人で楽しむために日々努力している方もいらっしゃるでしょう。
今回ご紹介するのは、そういった何かしらに打ち込んでいる方におすすめの一冊です。
なぜ反復練習によって技術が身に付き上達するのか、初級者・中級者と上級者の違いはどういう所にあるのか、上達した人はどこが違うのか、などの論理面だけでなく、効率よく上達するための方法論についても書いてあります。
中級者から上級者にレベルアップするためにどうすればいいのか、どんなスキルにも応用できる具体的な練習方法も紹介されています。
どうせするなら効果的な努力をしたいですよね。
(なごやの図書館スタッフ かえるまんじゅう)
こんにちは、もくもくです。
今回ご紹介するのは『みどりのゆび』です。
「じぶんの子どもをとてもかわいがっているのに、ほかのひとの子どもたちを
みなしごにするために、兵器をこしらえている」そんな父親のもつ兵器工場の
おかげで裕福な生活を送る少年 チト。
彼は不思議な力をもっていて、様々な人々や社会に触れ、本当に大切なものは
なにかを考え、行動を起こしていきます。彼の持つ力を使って街中を花で
満たし、人々を笑顔にしていったのです。
父親の兵器工場で作られた武器を使った戦争が始まろうとした時、
彼のとった行動は?その結果起きたことに父親はどんな対応をしたのでしょう?
公共図書館に所蔵されていますので、興味を持たれた方は
手に取ってみてください、少年が何者かがわかります。
そして最後にある「訳者のことば」も、是非読んでみてください。
この物語をより深く感じられると思います。
(名古屋の図書館スタッフ:もくもく)

 こんにちは、スタッフゆまたろうです。
こんにちは、スタッフゆまたろうです。
今回は「東京」を撮影し続ける写真家、
中野正貴さんのの作品集を紹介します。
『東京』
まず目を引くのが誰もいない東京。
銀座・六本木・新宿・渋谷、
世界有数の人口密度の高い場所なのに、
写真の隅々まで目を凝らして探してみても、
人も車も全く見当たりません。
まるで人類だけが消滅してしまったかのような東京の姿。
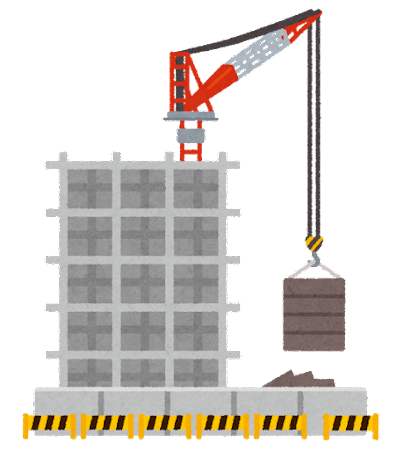

次に窓から見た東京。
生活感のある部屋の窓から見える、
東京に住んでいる者にしか見えない景色。
他にも水面に移る街の姿や、
製造中の巨大建造物など、
東京の様々な顔を見ることができておすすめです。
(なごやの図書館スタッフ ゆまたろう)
こんにちは、ポテトまるです。
今回は、浅倉秋成さんの『俺ではない炎上』の紹介です。
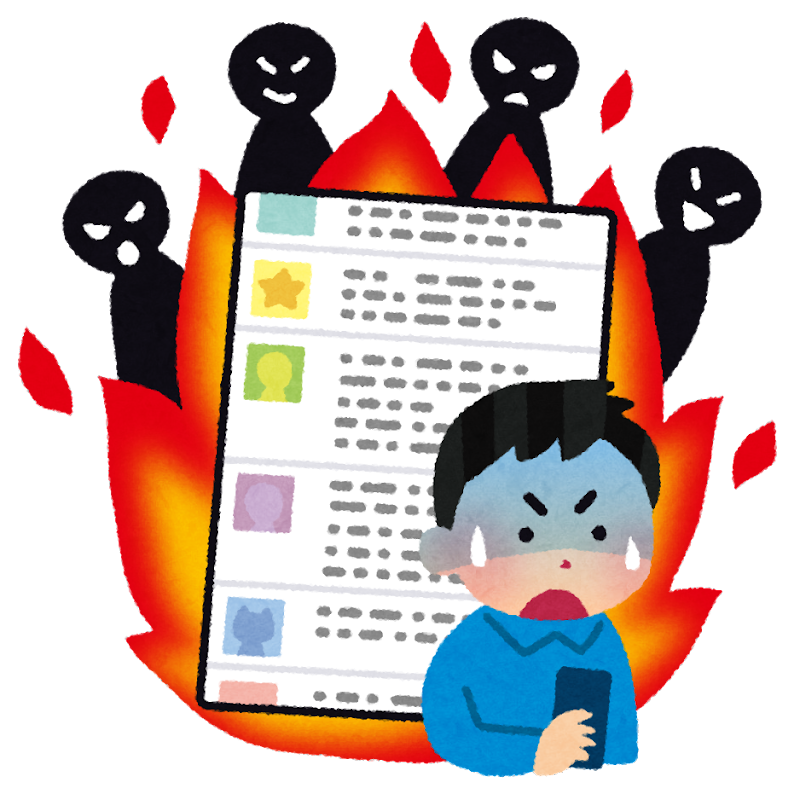
ある日、自分に成りすましたSNSアカウントの投稿から自分が殺人犯だと断定され、ネット上で次々と個人情報がさらされ、炎上してしまう。
自分が殺人犯ではないと知っているのは自分だけ。
日本中の人間が敵となり、自分を捕まえようとしている中、逃亡劇を繰り広げながら真犯人を探す。というストーリーです。
SNS上での炎上、そして犯人と思われる人物の個人情報の特定。これらは昨今、珍しくない時代になっています。
ネットの情報は誤った情報も多いというのは、よく言われていますが、あまりに不正確な情報が出回ってしまうと、あたかもそれが真実のように思われてしまうこともあると思います。
そういったSNSの怖さを疑似体験することのできる作品でした。
SNSという監視の目があることで、日本中が敵となってしまった主人公が繰り広げる逃亡劇は
とてもスリルがあって面白いと感じましたので、ハラハラとしたスリル感が好きな方にもおすすめの一冊です!
(名古屋の図書館スタッフ ポテトまる)
全盲の天才ピアニストとして知られる辻井伸行さん。
2009年の20歳の時にヴァン・クライバーン国際ピアノコンクールで日本人初の優勝を果たし、日本でも大きな話題になりましたね。
そんな彼が全盲で生まれてから今日唯一無二のピアニストになるまでの感動の物語が『ピアニスト辻井伸行奇跡の音色』に記録されています。
この書では、まだ彼が幼い時に出会い12年間向き合ってきた恩師川上先生との軌跡が紹介されています。
通常のレッスンではなく、目の見えない彼の為に時間をかけて譜面を録音テープで作成してあげる先生の情熱や、国際コンクールに向けての内幕など、読んでいてとても興味深いです。
常識と思われている練習方法も大切だけれども、自分に合った独自の方法でチャレンジすることの大切さ。それは勉強や部活にも当てはまることだと思います。
せっかくの才能の芽を摘んでしまわないためにも、物事を違った角度から見つめる柔軟さにハッとさせられました。
またこの書の中では、今まで彼が挑戦してきた曲が如何に難易度の高い物なのかをその都度言葉巧みに丁寧に紹介してくれています。
でもピアノ曲に明るくない私にとっては、そこが心にストンと落ちずになんとももどかしいです。
とにかく読んでいると辻井さんのコンサートに行きたくなること間違いなしです。
(瀬戸のスタッフ:かるみあ)
私はマクドナルドのビッグマックが大好きなのですが、
分厚いので、いつもテイクアウトして
箸で小分けにして食べています。
ネットで調べてみたところ、
かるく手で押しつぶしひっくり返すと食べやすく、
そしてマナー違反ではないのだそうです。
これなら店内で出来たてが食べられそうです。
このように、食べ方がわかれば食事の幅が広がります。
慣れない懐石料理や立食パーティー、
回転していないカウンターのお寿司はもちろん、
おなじみのひつまぶしや手羽先のからあげに、
吉野家やモスバーガーの食べ方など
イラストでわかりやすく解説する本を紹介します。
この機会に、自分の食べ方を見直してみませんか?
(数年前に食べた「ビッグマックジュニア」を定番化してほしい
なごやの図書館スタッフ ゆまたろう)
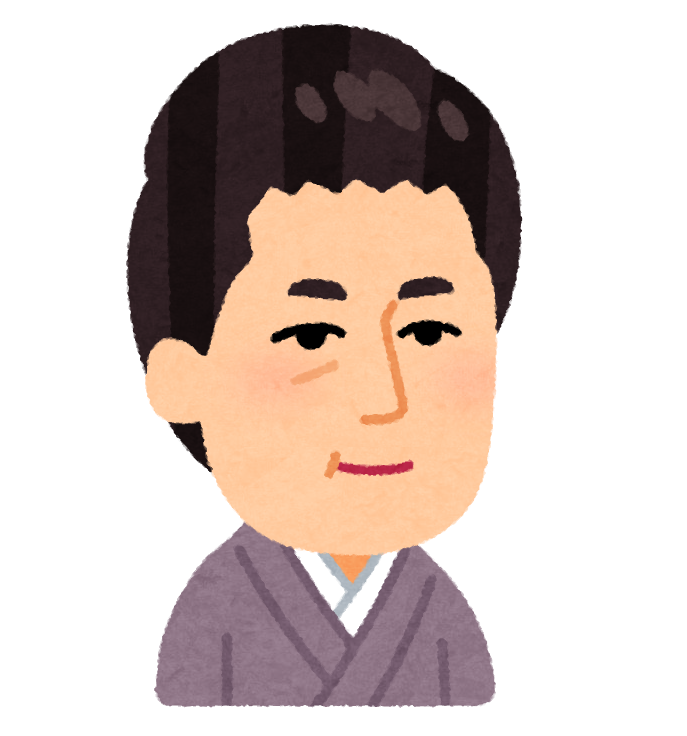
こんにちは♪ あかトマトです!
今日は曙館3Fしろとり図書館で展示されている図書の中から
ちょっと気になった1冊をご紹介します。
女性の権利のために闘った政治家や、平和のために自らの命をなげうって事実を伝えたジャーナリスト、文学や演劇、スポーツなどを通して日本の文化向上に貢献した人...様々な分野で活躍した日本の女性偉人たちがギュッと凝縮されて詰まっています。
何せ100人もところ狭しと掲載されているため、お気に入りをご紹介すると長くなってしまうので、ここは「百聞は一見に如かず!」ぜひ手に取ってご覧ください。
きっと皆さんの好きな分野で活躍した著名人も掲載されているはずですので、これを皮切りに詳しい研究書で深彫りしていくのもおもしろいかもしれませんネ☆
また、今回の『十冊十色』展は、見た目もわくわくするようなカラフルな展示となっていますので、お時間のある時にでも是非のぞいてみてくださいね♪
(名古屋の図書館スタッフ:あかトマト)
お待たせいたしました。
ただ今、瀬戸図書館では「教育実習」に備えた図書を展示しています。
展示コーナーをチェックしてくださいませ。
例年人気のおすすめ本から
今年新たに追加した本など30冊を展示しています。
『教育実習のよりよい授業づくり : 単元指導計画&学習指導案で学ぶ 新版』
『絵本で広がる小学校の授業づくり : 豊かな心と思考力を育む』などなど。
緊張する教育実習かと思いますが
体調に気を付けてくださいね。
皆さんの頑張りを応援しています。
(瀬戸図書館スタッフ 小豆)
人口1000万に満たない小さな国イスラエル。なぜこれほど世界のトップニュースになるのだろうか。
パレスチナとの武力衝突、イスラエルからの直接攻撃など、ニュースでやネットで現地の悲惨な状況を目にする機会が多い。国同士が争う理由は分からなくても、家を失い、家族を失い傷ついた人を見るたび心が痛む。
イスラエル人とパレスチナ人はどちらが正しいのか、どちらも間違っているのか。「どちらも、自分ではどうにもならない力の、お互いの、そして、自分自身の犠牲者なのである。」それをあぶりだす試みを著者は行っている。
この世界で最も複雑で、やっかいで、古代から続く紛争に注意を払うべき理由、紛争の解決を求める人びとを支援することが、中東のみならず世界にとっても重要である理由を語る物語である。国際社会の一員として"この国"を正しく理解するための入門書。
ぜひ、お読みください。
『イスラエル 人類史上最もやっかいな問題』/ダニエル・ソカッチ著
瀬戸の図書館員 とらねこ探偵ミロ