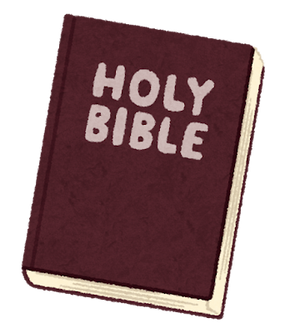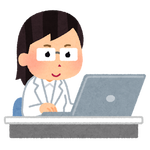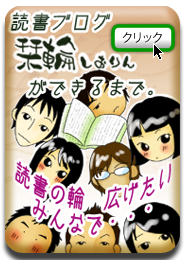オススメ本の最近のブログ記事
映画化やドラマ化された作品も多く知名度の高い作家、宮部みゆき。
社会派ミステリー作家というイメージが強いが、時代物なども幅広く手掛ける。
最近は、面白いけど現代の世相を反映してやや暗い内容に感じる。
個人的には、初期頃の作品が特に良いと思っている。
そんな作品を紹介したい。
休職中の刑事は、遠縁の男性に頼まれて彼の婚約者の行方を捜すことになった。
いったい彼女は何者なのか? 謎を解く鍵は、凄惨な人生に隠されていた。
余白を残したラストが気に入っている。
(瀬戸のスタッフ:emirin)
こんにちは、ポテトまるです。
今回は、『地雷グリコ』という作品を紹介します。
このお話は、女子高生が風変わりなゲームに次々と巻き込まれていく本格バトル小説です。
いったい風変わりなゲームってなに?と思いますよね。
実際に例を挙げると、多くの人が子供のころ遊んだことのあると思われる、じゃんけんをし、勝者が階段を進んでいく"グリコ"をアレンジしたもので、階段の途中に地雷装置を仕掛け、相手にいかに地雷を踏ませるか戦略を練りながら、ゴールを競う「地雷グリコ」というゲーム。
このゲームは、ただじゃんけんをするだけではなく、相手が何を出すのかや、どこで何回相手に勝たせるかなど様々に思考を巡らせ、相手が仕掛けた罠の位置を読みあいながら戦うという、とても頭を使うゲームになっています。
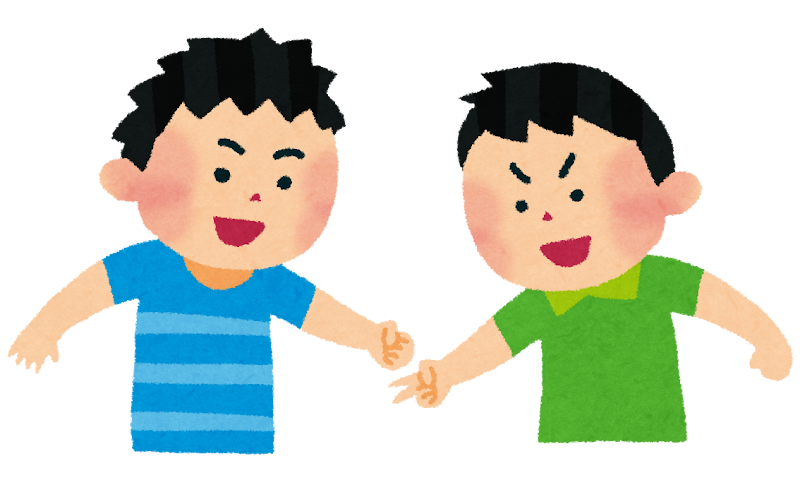
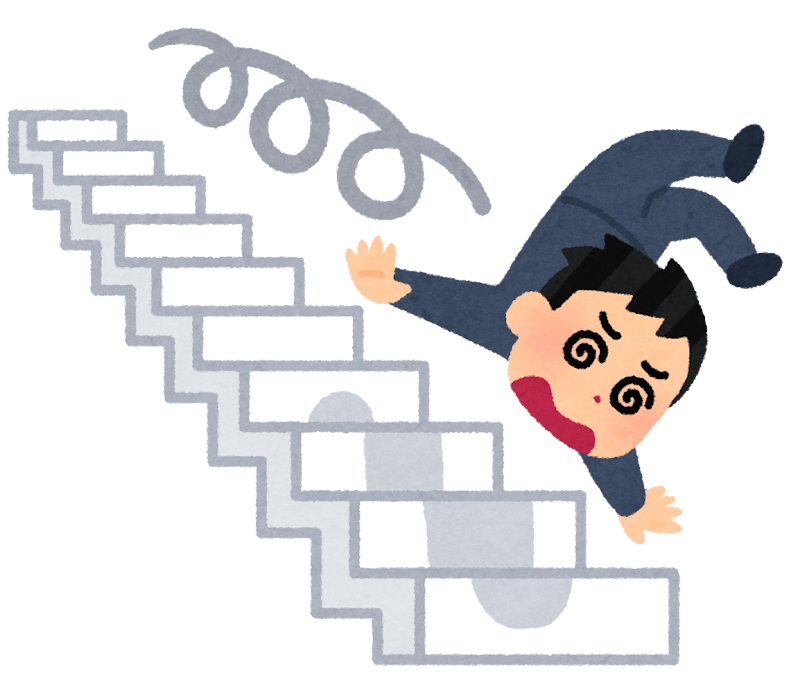
このほかにも「だるまさんがころんだ」や「ポーカー」など誰もが知っている遊びに独自ルールを加えたゲームがたくさん出てきます。
頭脳バトル小説と銘打っているだけあって、ゲーム中の駆け引きが高度。何気ない会話の中にも策略が潜んでいたりしたので、理解しながら読んでいくのは中々大変でした...。
ですが、読者も登場人物と一緒に勝負を見守りながら先の見えないハラハラとした緊張感を味わうことができて、楽しく読むことができました。
ゲームが好きな方など、普段小説は読まないという人にもおすすめの一冊です!
(名古屋の図書館スタッフ ポテトまる)
こんにちはおはぎです
本学はキリスト教系の大学ですが
中には元々キリスト教徒でない学生も多くいます
そうした学生にもキリスト教関係の講義を受ける機会があり
ここで初めて聖書に触れる方もいるのではないでしょうか
聖書は世界で最も読まれている本、と言われています
その聖書とはなにか、どんなことが書かれているのか
わかりやすく解説した本もいろいろあります
今回はそんな一冊を紹介します
聖書というと思い浮かべるのはキリスト教の
旧・新約の聖書が多いかと思いますが
これは聖書の一部であること
旧約聖書と新約聖書のそれぞれに
どんなことが書かれているのかを
図解付きでわかりやすく
解説してくれます
聖書を実際に読む前に、または読んだ後のまとめにも
こちらも併せて読んでみてはいかがでしょうか
(なごやの図書館スタッフ おはぎ)
こんにちは、スタッフあまりんです。
今回は映画化された話題作の原作を紹介します。
『#真相をお話しします』

マッチングアプリやリモート飲み会、
YouTube配信などを題材に
読んでいると気持ちの悪い違和感を感じ、
最後は大どんでん返しを迎える短編を5つ収録。
そのうちのひとつ「#拡散希望」は
第74回日本推理作家協会賞・短編部門を受賞していて、
公式サイトで全文を読むことができます。
https://www.shinchosha.co.jp/special/shinso/
映像化されなかった話もあるので、
映画を見てもっと違う真相も知りたい!
と思った方もぜひ読んでみてください。
(なごやの図書館スタッフ あまりん)
映画化やドラマ化された作品も多く知名度の高い作家、東野圭吾。
どれを読んでも面白く、ドラマ化された『ガリレオシリーズ』も有名。
個人的には、初期頃の作品が特に良いと思っている。
そんな作品を紹介したい。
一言で言うと、暗い。救いようがない。
偽りの人生を生きてきた男女。
女の二面性が徐々に明らかに...
その男女と、過去の殺人事件が結びついていくところが面白い。
(瀬戸のスタッフ:emirin)
こんにちは、もくもくです。
今回も、書名に惹かれて手に取ってしまいました。
『しっぽ学』思わず二度見するタイトルです。
しっぽから人を知るために、ある時は生物学、ある時は人類学
そして発生生物学や人文学。
文系理系に囚われず、柔軟に研究を続けている著者の奮闘記です。
どうしてしっぽ学を専攻するにいたったかなどを、その魅力とともに専門的な話を
交えてわかりやすく語ってくれます。
本当にしっぽについて研究している方がいたとは!驚きです。
進化に関することだけでなく、史料学まで真剣に取り組む著者のしっぽ愛と、
その研究のために生じる様々な壁を、力強く乗り越えていくすがたは、
とても素敵で、つい応援したくなるような楽しい1冊でした。
(名古屋の図書館スタッフ:もくもく)
こんにちは♪ あかトマトです。
皆さんは競馬というと、どんなイメージをお持ちでしょうか?
やはり"賭け事"という側面が大きいですよね。私もつい1年前まではそうでした。
でも家族が競馬にはまったことから、テレビでG1レースを見ることが多くなり、私も競走馬の美しさと強さの魅力に取りつかれてしまいました。
ちょうど今秋の日曜劇場で、競馬の世界を舞台にした『ザ・ロイヤルファミリー』(早見和真著)が放送されていましたネ!

こちらはしろとり図書館にも所蔵があります。
この作品では、G1の中でも「有馬記念」という年末に行われるレースで勝つことを目標に描かれています。
有馬記念は人気実力ともに兼ね備えた馬が選ばれ、その年の集大成ともいえるレースなので、ドラマの題材となるのも納得です。
ここからは余談になるのですが...私の推し馬は「シャフリヤール」と言います。
ドラマ『ザ・ロイヤルファミリー』第5話の日本ダービーで使われた映像が、21年にシャフリヤールが当時1番人気だった馬を鼻差で破った映像でした。
テロップの「出演馬」の先頭に「シャフリヤール」の文字を見たときは、ついにシャフリヤールも俳優デビューかぁ...なんて思ったものです(^^;)
そのシャフリヤールは、去年の有馬記念が引退レースでした。
くじ運悪く大外枠(中山競馬場芝2500mでは、大外枠は不利と言われています)を引いてしまい、15頭中10番人気...それでもシャフリヤールは1着の馬に鼻差に迫る2着でゴール!!
悔しかったけど、最後にダービー馬としての意地を見せた姿に、競馬で初めて涙が出ました💦
さて、今年の有馬記念12/28(日)にはどんなドラマが待っているのか!
でも馬券が当たるより大切な事は、「全ての人馬が無事にゴールに戻ってくること」です。
クリスマスから年末の忙しい時期ではありますが、皆さんもお時間あれば、是非28日に有馬記念を見てみてくださいネ~🎵
それでは、楽しいクリスマス&よいお年を...(^o^)/ あ!来年は午年ですネ~🐎
(なごやの図書館スタッフ:あかトマト)
みなさんこんにちは、ピアノです♪
今回ご紹介する本は『コミックマーケットへようこそ:準備するから準備会』です。
「コミックマーケット」あるいは「コミケ」と言えばアニメや漫画が好きな人はもちろん、そういった物に馴染みのない方でも一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか?年によっては開催をニュースで報じられたりしていますしね♪
知らない方のために簡単に説明すると、コミックマーケットとはあらゆる作品の二次創作物を個人や大学サークルあるいは企業さんまで、ありとあらゆる方々が制作し販売しているイベントです!
固く言うと「同人誌を中心とする自費出版物の展示即売会」です。街中でよく行われている市場やマーケットの「コミック版」とイメージしていただければわかりやすいのではないかと。
このイベントに出店する人たちはこの日のために寝る間も惜しんで準備をし、当日を迎えています。そして購入する側もこの日を待ち望んでいる、そんなイベントなのです。
しかしイベントの開催には出展者と購入者の両者だけでは成り立ちません。そう「スタッフ」の力が大きいんです!イベントを裏から支える彼らをクローズアップした本こそ、今回私がご紹介する本であります!(前置きが長くなってしまいました)
さて、こちらの本を読んですぐ表が出てくるのですが(p.20)なんとこちらスタッフの組織図なのです。まるで企業みたいなのでぜひ自分の目で確かめてみてくださいね!驚くこと間違いなしです。
この本の著者おーちようこさんがこの他にも驚きポイントを冒頭で語っていますが、この本を読んだ人なら多かれ少なかれ同じ感想を持つと思います。一部をご紹介すると、

・スタッフ数は約3000人!
・全員ボランティア!
・3000人で75万人の参加者を迎えている!
ニュースでも取り上げられるような、世界でも有名なイベントがボランティアスタッフで成り立っていたとは・・・驚きですね。
そんなスタッフたちのお仕事内容は私たちの想像をはるかに超えるほど膨大です。その全容を知りたい方はぜひご一読を!
そしてスタッフの方々からのメッセージには必ずと言っていいほど「興味があったら一度スタッフ登録をしてみてください」という一文があります。東京開催のイベントですが県外から泊りでの参加も多いそうですよ!この本を読んだ数年後にはあなたがスタッフの一員として会場にいる・・・な~んてこともあるかもしれませんね♪
そうなったら私としては本を紹介した甲斐があったというもの!いつかそんな素敵な報告が図書館にやってきたら・・・カウンターでいつでもお待ちしています(^^)/
(なごやの図書館スタッフ ピアノ)
こんにちは、スタッフあまりんです。
新しく入荷した漫画の中から、ぜひ一度読んでほしい本を紹介します。
文化庁メディア芸術祭新人賞や「このマンガがすごい!」第1位など、
過去に数々の賞を受賞した作品です。
主人公は中学2年生のナツ。
ちょっと不思議な友達・ちーちゃんと過ごす日々の中で、
ナツは嫉妬や劣等感、罪悪感など、黒い感情に揺れながら成長していきます。
「欲しかったはずのものを手に入れても、心は満たされない」
そんな経験、あなたにもありませんか?
この作品には、思春期のもやもやだけでなく、
地方の閉塞感や貧困、発達特性など、現代社会のリアルが静かに描かれています。
読後、胸の奥に小さな痛みが残るかもしれません。
でもその痛みが、きっとあなたの心に何かを残してくれるはずです。
1巻完結で、すぐ読める作品です。
気になった方は、ぜひ手に取ってみてください。
(なごやの図書館スタッフ あまりん)
ごきげんよう、スタッフのかえるまんじゅうです。
警察小説はミステリではメジャーなジャンルで、様々な切り口の作品が数多く存在します。
今回ご紹介するのは、その中でも異色の警察ものです。
『機龍警察』

〈あらすじ〉
機甲兵装と呼ばれる近接戦闘兵器が普及し、組織犯罪が凶悪化、大規模化するなか新設された警視庁特捜部は、最新鋭の機甲兵装である〈龍機兵〉を導入し、搭乗員として3人の傭兵を警部待遇で雇った。
特捜部の刑事たちと〈龍機兵〉が連携して、国内外を揺るがす凶悪な犯罪に立ち向かう人気シリーズ第一作目。
現実の国際情勢や社会問題とリンクしたテロや犯罪の生々しさと、迫力あるアクションシーンの数々は読みごたえたっぷりです。
今までにシリーズ長編6作と短編集1作が刊行されていて、さらに最新作がハヤカワミステリマガジンにて連載中です。シリーズを追うごとにどんどん面白くなっていくので、気になった方はぜひ続きの作品もチェックしてみてください。
(なごやの図書館スタッフ かえるまんじゅう)