身近なところを歴史探検(NO4)
名古屋市内からは北西に位置し、JR名古屋駅を京都・大阪へ向かう下り新幹線に乗る
と程なく右手前から目に飛び込んで来るお城(天守閣)が清州城です。この城は城址に建
つものではなく、天守閣のみを再現した模造の建物です。実際の城址はもう少し北側に位
置する清須公園 (清須市) 内にあります。建物は徳川家康が現在の名古屋城の位置に移した
為、この地には残っていません。しかしながら、この地は室町から安土桃山時代にかけて
尾張国の中心地であり、当時の守護の斯波氏が守護所を置き、後に守護代の織田氏が城を
置きます。かの今川氏との「桶狭間の戦い」に織田信長はこの城から出陣し、その戦後
この城にて徳川家康と清州同盟を結びます。信長は天下布武を掲げ、居城も、小牧、岐阜、
安土と替えてゆきますが、織田氏の拠点ともいうべき場所です。この場所が再び脚光を
浴びるのが、本能寺の変の後、羽柴(豊臣)秀吉が明智光秀を討った後、亡き信長配下の諸
将が集まり、織田家の家督をいかに相続すべきか協議が行われた場所になった時です。
ここでの秀吉の動きを振り返り、分析した書が『清須会議』(天下取りのスイッチはい
つ入ったのか)です。清須会議において秀吉は、信長の次男、三男である織田信雄、
信孝兄弟、家臣の筆頭であった柴田勝家を排除し、その後、実力者、徳川家康を凌駕し、
天下取りに邁進します。この会議は、切り札を手中にし、奇策をもって常に相手の動き
を封じ、流れを自らに引き寄せるという秀吉ならではの戦略手法に磨きがかかった出来
事でした。
(しろとり図書館スタッフ 東空)
カテゴリ:
トラックバック(0)
このブログ記事を参照しているブログ一覧: 身近なところを歴史探検(NO4)
このブログ記事に対するトラックバックURL: https://blog.ngu.ac.jp/mt/mt-tb.cgi/8611
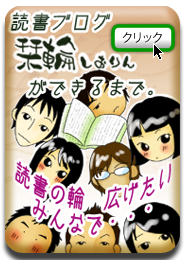
※画像をクリックすると漫画の原稿が表示されます。
蔵書検索
検索
最近のブログ記事
アーカイブ
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年4月
- 2013年3月
- 2013年2月
- 2013年1月
- 2012年12月
- 2012年11月
- 2012年10月
- 2012年9月
- 2012年8月
- 2012年7月
- 2012年6月
- 2012年5月
- 2012年4月
- 2012年3月
- 2012年2月
- 2012年1月
- 2011年12月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年9月
- 2011年8月
- 2011年7月
- 2011年6月
- 2011年5月
- 2011年4月
- 2011年3月
- 2011年2月
- 2011年1月
- 2010年12月
- 2010年11月
- 2010年10月
