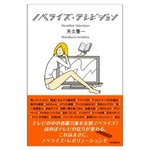皆さま、こんにちわ!
「笑っていいとも!」というテレビ番組を知っていますか?
ある世代以上の大半の方はご存じなのではないかと思う、
有名な番組ですね!!
タモリさんの名司会で放送され、
2014年3月31日に、皆に惜しまれて終了した長寿番組です。
かくいう私も学生時代、お昼の時間に家にいることができて
テレビを見られるときはたいていこの番組をみていました。
(社会人になってからはなかなか見られなかったのですが...)
番組放送終了を前後して、このタモリさんについて
書かれた本がいろいろ出版されていますね。
最近のようにタモリさん自身について書いた本もありますが、
今までもそれと書いてあるわけでない本でも、何かの拍子に、
タモリさんをたとえに出してる小説なんかは山ほどあるんじゃ
ないかと思います。
今回はそれともちょっと違う、タモリさんも登場しちゃう、
なんだかおもしろい本を紹介したいと思います。
『ノベライズ・テレビジョン』天久聖一著
この本、いろんなテレビ番組や、CMなんかの出演者や
その周辺の人たちの視点でかかれた妄想短編小説です(笑)
あくまでフィクション作品なんですが、みんなが知ってるあの人が、
こんなこと考えてんじゃないかな的な、こんなことあったかもな的な、
ていうか、もう本人とかじゃなくなんか完全に別世界の話的な(笑)
いろんな短編がのってます。
ひとつひとつは短い話なのですぐ読めちゃいます。
もとの番組知ってるとなんとも面白い。
ぜひ授業の合間に時間ができちゃったときとか、
ちょっとした笑いに出会いたいとき、
図書館にきて読んでみてはいかがでしょうか。
(名古屋のスタッフ:るん)