さー、今回のブログは長くなりそうです。
建学の精神「敬神愛人」の「愛人」に関わるからです。
創世記2章~ その5の続きです。
『主なる神は言われた。「人が独りでいるのは良くない。彼に合う助ける者を造ろう。」』
日本聖書協会『聖書 新共同訳』創世記 2章 18節
ということで動物がつくられました。
しかしアダムは動物のなかに"自分に合う助けるもの"を見つけられませんでした。
そこで神はアダムが眠ると、彼のあばら骨の一部をぬきとって、その骨で女(エバ)をつくりました。
目覚めたアダムはエバと出会います。彼は独りではなくなり、自分に合う助けるものと出会いました。
これを男女関係だのアレコレ抜きにして考えるとすごく大切なことが含まれています。
ある"平和"についての話しの中で、
もし世の中の人間がたった一人だったら平和だろうか?
という提議がありました。
戦争は一人じゃおこしようがないし。
人と傷つけあうことがないのが平和なら、一人じゃできないから、平和じゃない?と・・・
でも一人じゃこれっぽっちも幸せになれそうにないなー。そんなん平和じゃない。
一人ぼっちの平和なんてイヤじゃないですか?
その時にこの「人が独りでいるのは良くない。彼に合う助ける者を造ろう。」に注目しました。
なんで一人じゃなく、独りなんだろう?
もし一人じゃなく何人もいても、独りじゃ意味がないってこと???
平和って争いがないこと、ではなく、みんなが独りじゃないことで、
敬神愛人の「愛人」って、人を独りにしないことじゃないかな。
独りでいる人によりそうことが隣人として共に生きていく愛なら、 敬神愛人を実行することは平和を実現することになる。
そんな想いを創立者のクライン博士はもっていたのでしょうか。
ひとまず創世記2章はここまで。
1章では、光→天(空)→海と地と植物→太陽と月→魚と鳥→動物と人間の順番で世界が創られたのに・・・
2章からは天地→アダム(男性)→植物→動物→エバ(女)の順で創造されています。
これについての解釈やら、他にもあれやこれや???なとことかありますが、それはまた別の機会に・・・あ、キリスト教センターでは随時『聖書を読む会』がありますので、気になる方はどうぞご利用ください。
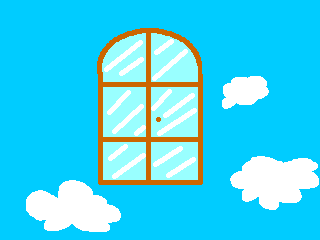 ↑こんなかんじですかねー。
↑こんなかんじですかねー。