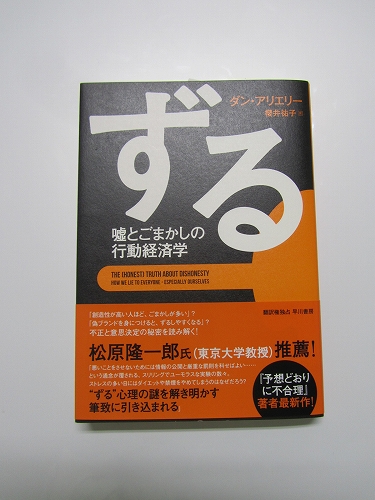本日は、「着こなし講座」と「業界セミナー」がありました。
「着こなし講座」では、青山商事さんに来ていただき、スーツの着こなし方や選び方、手入れの仕方などについて伝授していただきました。
最後にはスーツの割引券ももらいましたよ♪
「業界セミナー」では、海運・住宅業界の方に来ていただきお話してもらいました。
必要な資格はなんですか?という質問に対して、
海運会社では「通関士」があるといいが、必ず必要ではないので余裕があったらとっても良い。
住宅会社では、「宅建」と「FP」が持っていると、学生のうちに取っておくといいということでした。
「業界セミナー」は明日の公務員がラスト!
「着こなし講座」1月19日にあるので、ぜひ参加してくださいね。
そしてそして
1月20日に開催される「就活カフェ」の告知もキャリアデザインの授業でさせてもらいました。
約30名の様々な業種の内定者の皆さんに来てもらうので、
3年生の皆さんは、ぜひイベントに遊びに来てください!!