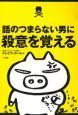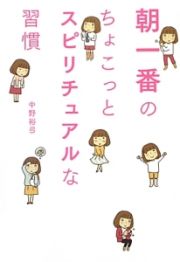学生さんと先生を繋ぐ連続企画★Bridge★、今回の先生は・・・
商学部教授 宝島 格 先生です。
先生は、2013年現在、入学センター委員をしておられます。
AOやオープンキャンパスでお世話になった人もいるのでは?
■■■ どんな思いをもって、授業(ゼミ)に臨まれていますか? ■■■
常識を持ち、筋道立てたものの考え方を身につけ、良い批判眼を育てる。
私は、学生さんには、常識をもって、色々なことをきちんとやってくれる + 想像力・アイディアのある人間になってくれたらいいな、と思っています。いわゆる「専門バカ」にならず、色々な事を見聞きして欲しい。筋の通ったものの考え方ができるようになってほしいのです。
私は、数学関係の授業を受け持っています。私の授業は真面目な感じがすると思います。脱線したり適当にメリハリをつけるということはあまりなく、時間めいっぱい、しっかり授業をします。知らない知識を教えるという授業ではなく、現状持っている理性を活かして、普通に考えれば結論にたどり着けるような問題を選んでいます。演習のような、自分で実際に考えてみる小さな課題を出して解いてもらっています。この作業は、物事を筋道立てて考える訓練になります。自分で論理的に考え、授業を理解してほしいのです。「これこれこういう条件であれば、こうならざるを得ない」という、どうやってもひっくり返すことのできない状況の時があるので、色々な条件を考えて物事に対峙しなくてはならないよ、という事が伝わるといいなと思います。
教養科目の授業内容は、今すぐには役に立たないような知識であるかもしれません。でも、教養として持っていることで、将来活きてくることもあります。
また、学生さんには、人に言われるままに物事を鵜呑みにしないで、良い意味で批判眼を持って、人の言うことに接するようにしてほしいと思っています。
常識を働かせるだけで、おかしなことを言っている人のアラは見えてきます。雑誌や週刊誌などは、ちょっと常識を働かせると「おかしい」と気づく場合があると思います。しかし、これがテレビや新聞になると、ぱっと見抜けないことがあります。でも、よく見聞きしてみると意外におかしいことも結構あるんです。メディアリテラシーを身につけて、情報に接してほしいですね。基礎統計学の授業では、数字を使って結論を出す場合に、「こういう間違いがある」「こういうごまかしがある」という例が、色々と出てきます。こういった題材を扱った、易しい本もありますので、読んでみるといいと思います。
■■■ 先生のお薦め本 ■■■
先生のお薦めの本は・・・
『チボー家の人々』
ロジェ・マルタン・デュ・ガール著 白水Uブックス 全13巻
内容は・・・読んでのお楽しみ。古典小説です。
この本を読むことで、若者は色々と考えることがあるのではないか、とのことでした。
ちなみに、先のお話に登場したメディアリテラシーに関する本では、
『「社会調査」のウソ リサーチ・リテラシーのすすめ』谷岡 一郎著 文春新書
という図書もご紹介いただきました。
是非、読んでみてくださいね。
■■■ 今日の一枚 ■■■
今回は、"先生のお気に入り"の写真です。
 お話を伺って、宝島先生は、登山家のような方だな、と思いました。
お話を伺って、宝島先生は、登山家のような方だな、と思いました。
色々な情報・条件をもとに自ら進むルートを決め、着実にコツコツと、それでいて臨機応変に、己と向き合いながら道を歩んでいく。また、登山家が大自然に謙虚であるように、先生も、お仕事やお話のご様子から、非常に謙虚な方だと感じました。実際、先生は登山をなさるそうです。でも、最近はなかなか登山に行けないのだそうです・・・
宝島先生にお話を聞いてみたいと思ったあなた、是非、研究室の扉をたたいてみて下さい。
さて、次回の★Bridge★は・・・
経済学部教授 児島 完二 先生です!
お楽しみに★
チョッパー子