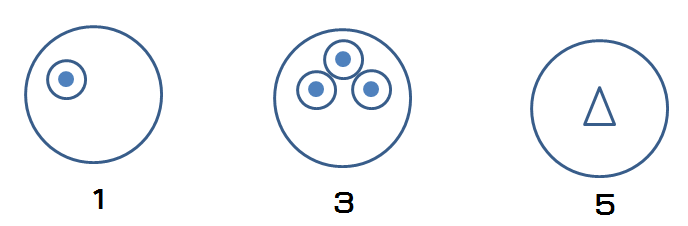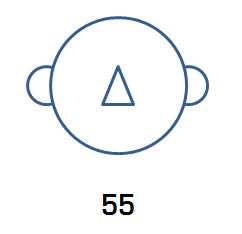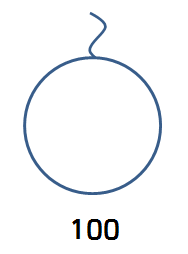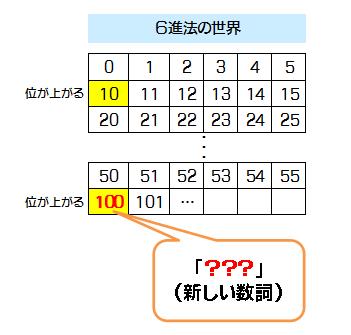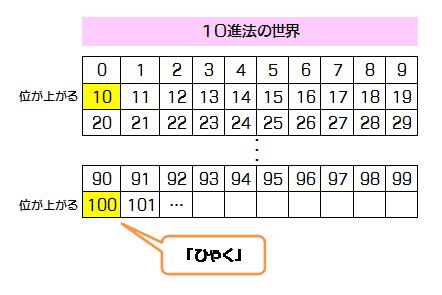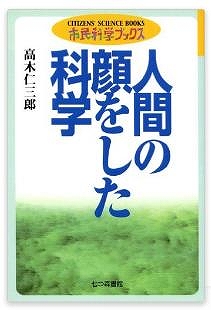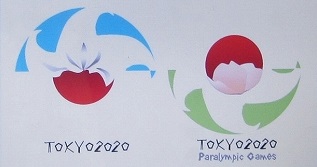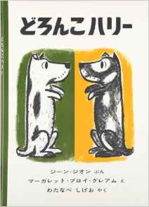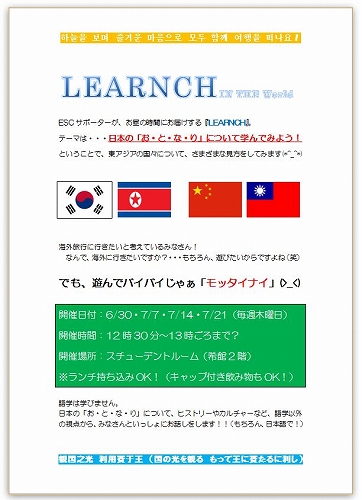みなさん、おはようございます、こんにちは、こんばんは!(^^)!
ESCサポーター、主幹の重松歩月(法学部法学科4年)です。
教育学習センター(通称:ESC)では、『ESCサポーター』になっていただける
学生のみなさんを大募集しています(>_<)(>_<)
【ESCサポーターって?】
私たち「ESCサポーター」は、希館1階教育学習センター(通称:ESC)のサポーター
として、授業やテストで解らないことなど、学生のみなさんが抱いている不安や疑問を
「みなさんと同じ視点」に立って、サポートすることを目的に活動しています。
【具体的に、どんなことをするの?】
例えば...
・みなさんに「楽しく学んでもらう」ため、さまざまなイベントを企画します!
・授業で困っていることや、授業を受けていても分からないことなどをサポートします!
・テスト勉強をしていて、解らないところなどを、いっしょに考えます!
『ESCサポーター』は、学生の本業である「勉強」について、
さまざまな方法・視点から、全力でサポート=お助けします!(>_<)(>_<)(>_<)!
【 なんか、家庭教師っぽくて、やれる自信が・・・】
安心してください!そんな「あなた」を私たちは求めています!
学生の本業である「勉強」をサポートする私たちは、家庭教師や塾の先生ではありません。
私たち『ESCサポーター』は、みなさんと同じ「学生」です!
つまり、学生だからこそ、先生とは異なる視点で、「仲間」としてサポートすることが
できるんデス(^O^)
みなさん、私たち『ESCサポーター』といっしょに、いろんなことに「チャレンジ!」
してみませんか?
詳しくは、CCS掲示板をご覧ください。
また、教育学習センター(希館1階S-プラッツと同室)へ直接でもOK!です。
~チャレンジする あなたの熱意 キャッチします!~
お待ちしています(>_<)!(^^)!!(^^)!(>_<)(>_<)(>_<)!(^^)!!(^^)!(>_<)!(^^)!
!(^^)!!(^^)!(>_<)(>_<)(>_<)!(^^)!!(^^)!!(^^)!!(^^)!!(^^)!(笑)